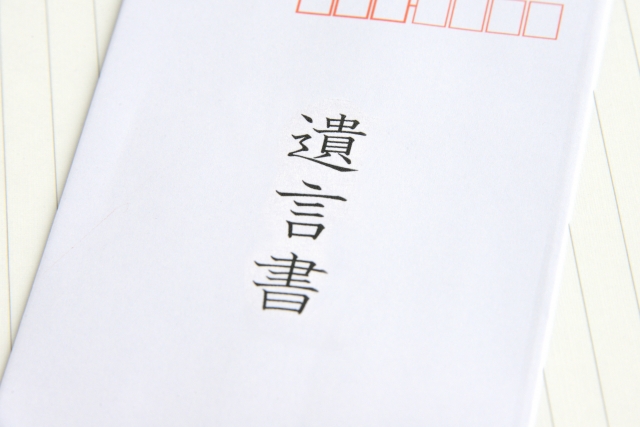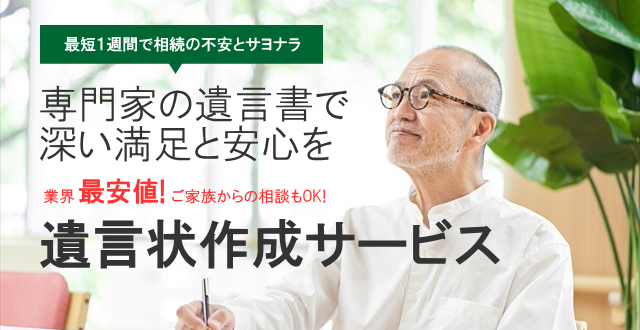
●外出不要!自宅で簡単に遺言書作成
当事務所では、リモートで遺言書を作成しております。遠方からでもオンラインで遺言書作成が可能です。ご相談、打ち合わせ、原稿完成までリモートで完結するので、最短1週間でご自宅から遺言書が作成できます。遺言書の作成は、何度でも書き直しが可能です。
●法的に有効な遺言書で安心!
行政書士が作る法的に有効な遺言書で、一生の安心が手に入ります。
●ご家族からの相談もOK
親御さんがご自分でお話をするのが難しい場合、ご家族からのご相談もうけたまわります。親御さんの遺言のお悩みもスッキリ解決します。
※但し、最終的には本人の意思確認が必要ですので、ご了承ください。
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。
無料相談はコチラ
遺言状サービス一覧
注意事項
※公証役場について
公正証書遺言は、最後に、遺言者ご本人様が公証役場に行かれるか公証人に出張していただく必要があります。ご依頼人様の公証役場への訪問には、証人2名の同席が必要になります。また、公証役場の手数料及び証人手数料は公証役場で直接お支払いただきます。
※資料収集について
原案作成の際、戸籍謄本、住民票、本人確認書類等、公正証書遺言に必要な資料収集を行います。この際、遺言者ご本人様の意思確認を行います。遺言者ご本人様からの依頼なら不要です。(ご家族からのご依頼の場合、電話、ZOOM、LINEのビデオ通話などによる)
※ご依頼完了までの期間について
ご依頼完了までの期間は、公証役場の予約状況により異なります。通常2~3週間かかる場合もございますので、ご了承ください。
※無料相談でご回答できないケースもございます。
1.ご友人、ご近所の方など、ご自身・ご家族以外の方の遺言に関するご質問
2.ご自身で作成された遺言状に関するご質問
3.知識の確認のためのご質問(法律や手続きに関するご質問は書籍かネットでご確認ください)
4.相続税、登記、争いに関するご質問(相続税は税理士、登記は司法書士、争いごとは弁護士の業務領域です。行政書士はご回答できません)
遺言状とはどういうものでしょう?
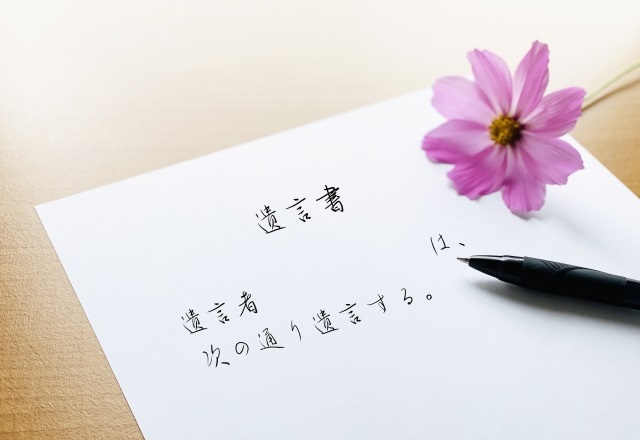
そもそも遺言状とはどういうものでしょう?
遺言状とは、最後まで自分らしく生きて、幸せに人生を閉じるための大切な手紙です。
あなたの生きた証を、残される人たちに伝える使者の役割を果たします。
良い遺言状が書けると、深い満足と安心が得られます。
遺言状を書くタイミング
①今すぐ遺言状を用意すべきケース【危急時遺言】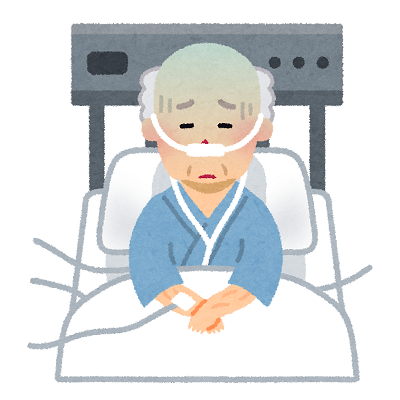 ・余命幾ばくも無い方で今すぐに遺言を残さなくてはいけない場合
・余命幾ばくも無い方で今すぐに遺言を残さなくてはいけない場合・病気や事故などで緊急事態となり、すぐに遺言書を作成しないと遺言者の生命が失われてしまう場合
こういった緊急事態の場合「危急時遺言」という特殊な形式を活用して遺言書を作成することをおすすめします。
» 詳しくはこちら
②急いで遺言状を用意すべきケース すぐに専門家に相談することをお勧めします
 高齢者が入院したり、既に入院している患者様の様態が悪化している
高齢者が入院したり、既に入院している患者様の様態が悪化しているもしくは年齢が90歳を超えた。
加えて、相続人に以下、1、2のいずれかの人が含まれている
1.相続人の中に、判断能力が十分でない人がいる
2.相続人の中に、関係が悪い人、連絡先が明確でない人がいる
③できるだけ早く遺言状を用意したほうが良いケース
 高齢や病気により施設に入所、長期入院、介護が必要になった
高齢や病気により施設に入所、長期入院、介護が必要になった加えて1、2、3のいずれかもしくは複数の条件が含まれる
1.相続財産に不動産が含まれていて相続人が2人以上いる
2.相続人の中に、判断能力が十分でない人、関係が悪い人、連絡先が明確でない人がいる
3.相続診断で『緊急度』『危険度』がどちらも高い
④そろそろ遺言状を残すことを考えておくケース
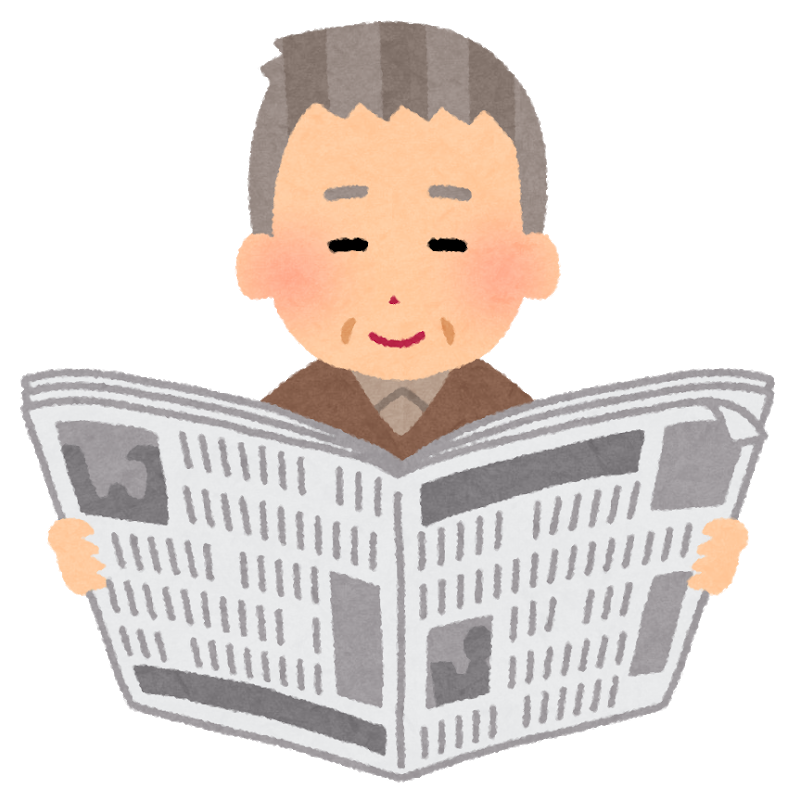 1.テレビや新聞で『相続』という言葉が気になるようになった
1.テレビや新聞で『相続』という言葉が気になるようになった2.相続について考えておかなければという気持ちになった
3.将来の健康や財産管理に不安がでてきた
4.妻、夫、子供たちの将来について不安がある
5.相続診断で『緊急度』は低いが『危険度』が高い
■お電話による相談予約をご希望の方は以下の番号ご連絡下さい。
受付:平日9:00~18:00
![]() 0120-549-343
0120-549-343
■メールによる相談予約をご希望の方はこちらをクリックして下さい。
受付:365日24時間
メールでのお問合せはこちら![]()